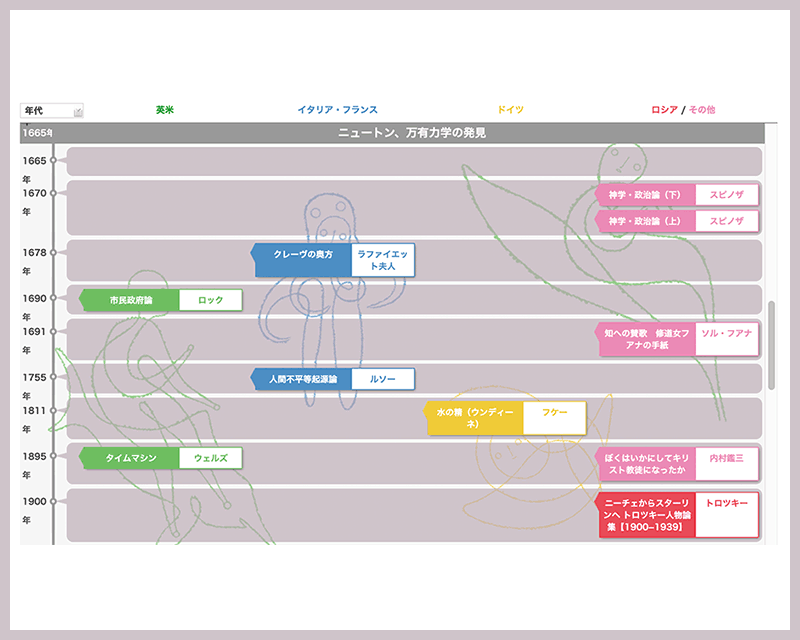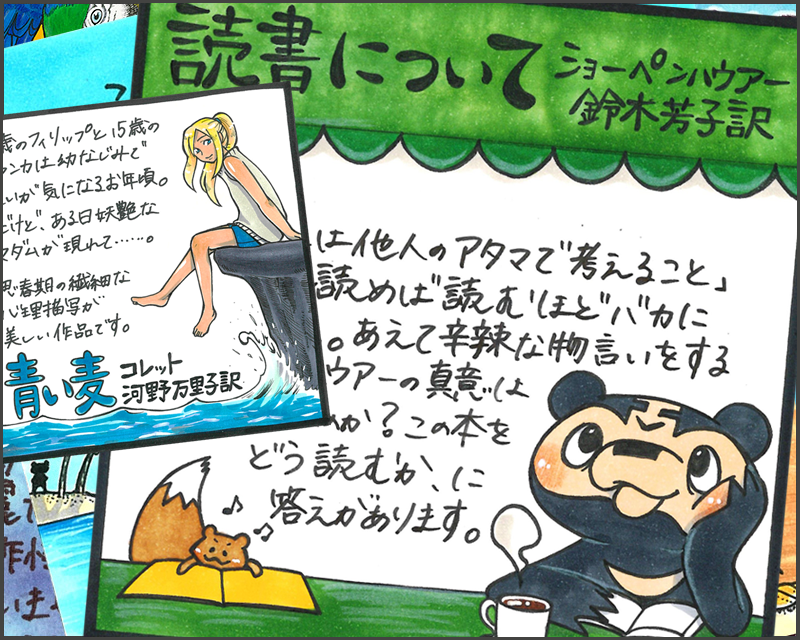【Zoom配信】紀伊國屋書店Kinoppy&光文社古典新訳文庫読書会#101 “ここにもあった、いとをかし。” 繊細かつユニークなまなざしですくい取った平安女子の日常。『枕草子』の世界観を味わう。 訳者・佐々木和歌子さんを迎えて

「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、少し明かりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。」今回取り上げるのは、このあまりにも有名な冒頭の段で知られる『枕草子』の新訳です。この「春はあけぼの」の出だしはほとんどの人が知っている(学校で習った)と思いますが、三百以上ある全部を読んだことのある人はそうはいないでしょう。文学史的には、『方丈記』『徒然草』とならび日本三大随筆の一つに挙げられる平安朝文学を代表する随筆です。
NHK大河ドラマ『光る君へ』の主人公まひろのモデルである紫式部と同時代を生き、才女でライバルとも呼ばれた清少納言は、物語ではなく随筆のかたちで宮廷生活のさまざまな一面を切り取りました。栄華を誇った中宮定子を支えた“ベテラン女房”らしい、優れた感性と鋭いまなざし(人間にも自然にも)ですくい取った数々の「いとをかし」。なかには今なら炎上必至の(?)の痛烈な悪口もあります。『桃尻語訳 枕草子』(橋本治訳)の衝撃は今でも鮮明ですが、今回の新訳では好奇心旺盛で進取の精神に富んだ女房である清少納言らしさはもちろん、定子サロンの自由な雰囲気も表れていると思います。
今回の読書会では、「清少納言は当時最高のコメディエンヌ」と評する訳者の佐々木和歌子さんをお迎えして、『枕草子』の魅力と読みどころと、訳文の工夫についても語っていただきます。
(聞き手:光文社古典新訳文庫・創刊編集長 駒井稔)
紀伊國屋書店Kinoppy&光文社古典新訳文庫読書会 #101
“ここにもあった、いとをかし。” 繊細かつユニークなまなざしですくい取った平安女子の日常。『枕草子』の世界観を味わう。 訳者・佐々木和歌子さんを迎えて
“ここにもあった、いとをかし。” 繊細かつユニークなまなざしですくい取った平安女子の日常。『枕草子』の世界観を味わう。 訳者・佐々木和歌子さんを迎えて

- 《日時》2024年6月24日(月)19:00~20:30
- 《会場》Zoom(オンライン)
- 《参加費》無料
- 《参加方法》2024年6月1日(土)~2024年6月24日(月)19:00の間、紀伊國屋書店ウェブストアにて、参加お申し込みを承ります。 ※ご案内メールを当日までにメールでご連絡します。
- お申し込みについて、詳しくは 紀伊國屋書店ウェブサイトをご覧ください
- [佐々木和歌子(ささき・わかこ)さんプロフィール]
- 1972年、青森県生まれ。文筆家。東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了。専門は日本語日本文学。(株)ジェイアール東海エージェンシーで歴史文化系コンテンツの企画制作に携わりながら、古典文学の世界をやさしく解き明かす著作を重ねる。著書に『やさしい古典案内』『やさしい信仰史――神と仏の古典文学』『日本史10人の女たち』など。訳書に後深草院二条『とはずがたり』がある。
- 佐々木和歌子さんのプロフィール詳細(光文社古典新訳文庫での訳書一覧)
- [駒井稔(こまい・みのる)さんプロフィール]
- 1956年横浜生まれ。慶應義塾大学文学部卒。’79年光文社入社。広告部勤務を経て、’81年「週刊宝石」創刊に参加。ニュースから連載物まで、さまざまなジャンルの記事を担当する。’97年に翻訳編集部に異動。2004 年に編集長。2年の準備期間を経て’06年9月に古典新訳文庫を創刊。10年にわたり編集長を務めた。著書に『いま、息をしている言葉で。――「光文社古典新訳文庫」誕生秘話』(而立書房)、『文学こそ最高の教養である』『編集者の読書論』(光文社新書)、『私が本からもらったもの 翻訳者の読書論』(書肆侃侃房)がある。